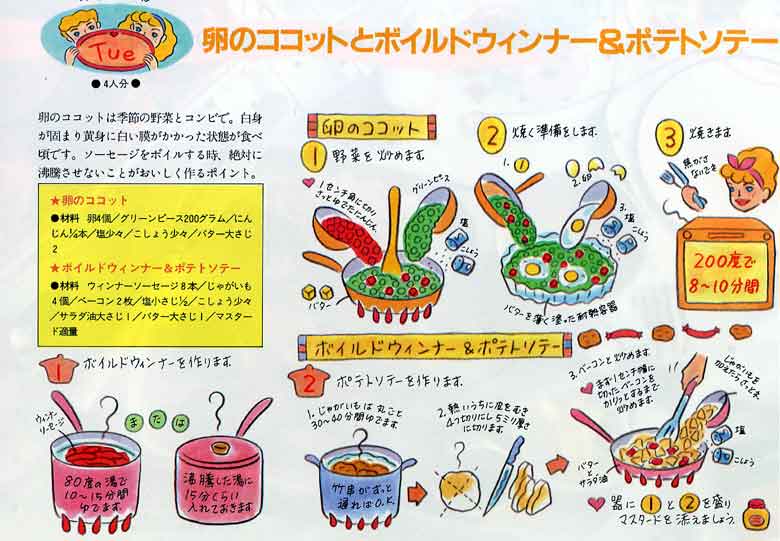|

|
これからの住宅は、世界の動きから見て高気密高断熱住宅へ向かうと思われます。
省エネルギーの流れが住宅にも取り入れられてきています。
進んでいるのはヨーロッパ諸国です。
特にスウェーデンが進んでいるようです。
寒いスウェーデンでは、断熱性を高くすることによって、暖房のためのエネルギーの節約が国の対策として進められています。
同時に夏の冷房のエネルギーも節約できています。
また、二酸化炭素問題、地球温暖化問題もクローズアップされてきていますので、住宅の省エネ化、断熱化はどんどん進むはずです。
茅葺の民家の夏の涼しさは今の家とは比べものになりません。
しかし、日本の家は夏涼しく住めるようにつくられているため、気密性はまったくありませんでした。
戦後新建材の普及により、断熱性は一挙になくなってしまいました。
その後断熱材が普及しましたが、湿気の多い日本では結露が問題になりました。
断熱材を入れることによって、結露し住宅の耐久性が低下するのです。
現在エアコンをつけるのは当たり前の時代です。
夏に家をあけることによって涼しくしていたのが、エアコンによって涼しく生活する時代になりました。
最近ではセントラル冷暖房を組み込んだ住宅もでてきています。
さらに、太陽光発電等をつけることも可能です。
太陽熱発電には国からの助成金があります。
快適性、省エネ性を考えれば絶対お勧めします。 |
|
|
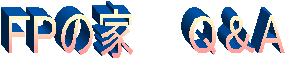
|
|
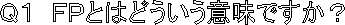
|
|
FPとは、フレーム(Frame)&パネル(Panel)の略。
フレームは軸組のことで、パネルはウレタン断熱パネルのことです。
軸組の柱や梁の間にウレタン断熱パネルをはめ込むため、このように名付けました。
現在、FP工法には、2×4工法もあるためFP軸組工法、FP2×4工法と呼んでいます。 |
|
|
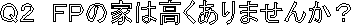
|
|
硬質ウレタンは建材としては高価であり、高級断熱材としてのみ使用されてきました。
もちろんこれを採用してFPの家は、従来の住宅よりも高価です。
しかし、断熱性、気密性、高耐久性、高防湿性など様々な優れた特性を持つ硬質ウレタンは、断熱材としては理想的なものです。
また、硬質ウレタンを使用することにより家の寿命が延び、ランニングコストも安くつくため、長期的に考えるとさほど高いとはいえません。
そのほかに、コストの軽減を図るためウレタンパネルを製造する専用工場を設け、流通コストの削減と生産性を向上させています。
また、パネル化を行っているため現場施工の簡略化と工期の短縮も図られており、このことによってもコストの軽減のための努力をしています。 |
|
|
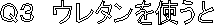
|
|
確かにウレタンパネルは、石油科学製品ですので、全く燃えないということはありません。
しかしウレタンパネルには難焼剤をミックスしてあり、その発火温度は木材とほぼ同様の250℃前後の範囲となっています。
また、ウレタンパネル内はウレタンが隙間なく充填されているために必要な酸素が供給されず、火がグラスウールのように走ることはありません。
しかもウレタン発泡体は自消性があり、表面が炭化した状態になり、それ以上燃え広がりません。
このように、ウレタンを使うと一般工法よりも火災に強いと言えます。 |
|
|
|
|
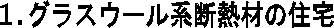
|
|
グラスウール繊維には、その特性上吸湿性があります。
また、一度湿ってしまうと壁体内に納めてある為、ふとんの様に干すことができません。
しかも、湿ることにより、その断熱性能は、ダウンしてしまうと共に、木材を腐らせてしまいます。
グラスウール自体は、気密をとるための資材ではなく、気密シートなどにより、気密化を図らざるを得ません。
この気密をとる作業が、手間のかかる作業であり、しかも、施工ムラが生じ易い作業です。 |
|
|
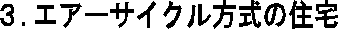
|
|
この住宅に言えることは、高気密高断熱住宅ではないということです。
また、理論どおりに、空気が循環しているかどうかに関しては、疑問が残ります。
季節変化、風と太陽方向の関係、隣地の建築物などの影響を受け、空気の動きは建物1棟ごとに変化してきて当然です。
特に南面の暖かい空気が、北面をおりた場合、冷やされて結露が発生する恐れもあります。 |
|
|
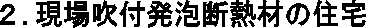
|
|
この現場発泡方式では、圧力をかけて、人工的に、均等に発砲させることができないため、気泡体の構造がまちまちとなり、大きなエアーだまりが生じたりします。
つまり、断熱性・防水性などが、気泡体のムラにより、部分部分で低下してしまうのです。
また、気温や発泡機の影響により、二次発泡が生じたり、一度発泡したものが縮んだりと品質が安定しません。特に低温時では、被吹付表面温度が5℃以下となった時に、吹き付け断熱材が割れたり、(亀裂)接着が低下し、はがれてきたりなどのトラブルが生じる可能性があります。 |
|
|
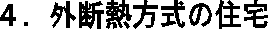
|
|
この方法の場合、断熱材の厚さ分が、まるまる外側にはみ出してくるため、窓枠やドア枠などの部材も、通常の寸法と異なり、下地などが普通よりも多く必要となります。
同様の理由から、施工に手間がかかるため、施工ムラが生じ易いと言えます。
気密の問題でも、桁まわりやつなぎ目の部分など施工が行いにくく、特に下屋のある住宅などは、気密化を図ることが、難しい状況になっています。 |
|