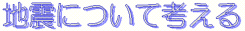 |
| 〜日本で発生する地震について〜 |
| 1.地震プレート |
日本に関係するプレートは4枚あり、「太平洋プレート」はほぼ西向きに、「フィリピン海プレート」は北北西の向きに向かい、日本列島を乗せている「ユーラシアプレート」「北米プレート」の下にに潜り込んでいます。世界の地震の1割は日本周辺で発生しており、日本は最も地震の多い国といえるでしょう。特に、静岡県周辺はこの4枚のプレートが地下で接しているという、大変特異な場所にあります。
日本の太平洋沿岸の海底では、海洋プレートが陸のプレートの下に沈み込んでおり、これらのプレート境界では、プレート先端が跳ね上がることでマグニチュード8クラスの海溝型地震が発生する事がしばしばあります。 |
| 2.大地震の起きる種類と日本の地震の歴史 |
| 日本付近で起きる大地震は、下記のほぼ4種類に分類することができます。 |
| (1)プレートの境界方地震(例=1994年三陸はるか沖地震) |
| (2)浅い場所でのプレート内部破壊による地震(例=1994年北海道東方沖地震) |
| (3)深い場所でのプレート内部破壊による地震(例=1993年釧路沖地震) |
| (4)地表近くの活断層による地震(例=1995年兵庫県南部地震) |
| 3.大地震の起きる可能性 |
| 国の地震調査委員会では強い地震の揺れに見舞われる確率を地域ごとに色分けして示す「地震危険度マップ(地震動予測地図)」を2005年3月までに全国で完成させる予定。 |
●2002年5月山梨周辺試作版を発表した。
「今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる危険性がかなり高い(確率6%)と判定。山梨県は東海地震の想定震源域に近いことに加え、糸魚川-静岡構造線断層帯(長野県-山梨県北西部)」など三つの活断層に囲まれている。こうした地位理的条件から、強い揺れに見舞われる危険性の高い範囲が広域化した。 |
●2003年3月北日本試作版(北海道・東北版)を発表した。
北海道東部の太平洋側と、三陸沖プレート(岩版)境界に近い宮城県北部が「今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率が非常に高い(確率25%以上)」と判定された。※この後、2003年5月26日の宮城県沖地震が発生 |